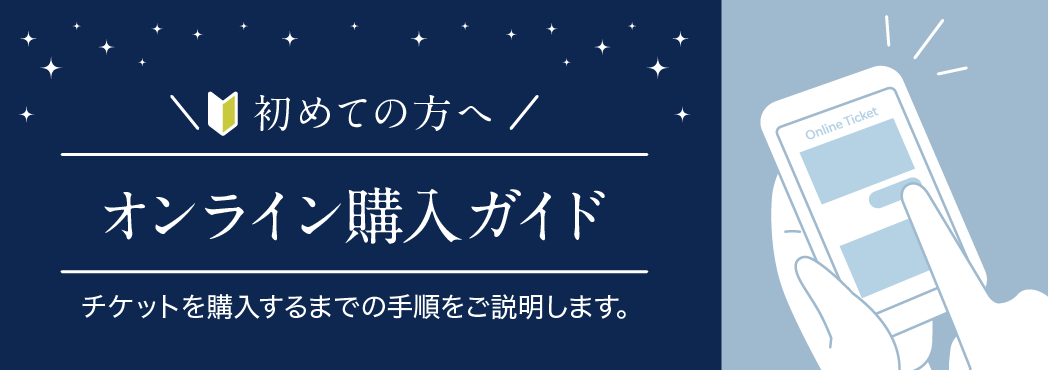「音楽」と「宇宙」の深い関係性
「宇宙は、数学という言葉で書かれている」というガリレオ・ガリレイの有名な言葉を俟つまでもなく、私たちは数学の言葉で宇宙を理解しています。その一方で、音楽は音の芸術であり、音は、媒体の振動によって発せられる現象ですから、音階、和声、倍音などすべてが物理的現象であり、数学の対象になります。つまり、宇宙も音楽も、数学の言葉を介して理解されているということです。しかし、数学は理性に訴えるものであり、音楽は感性に訴えるものですから、同一視はできません。にもかかわらず、人間は、惑星系の公転周期の数系列を、音の倍音列になぞらえたり、ボイジャーが聴いた宇宙電波を、可聴領域に移して音楽として聴いたりしています。その背景には、宇宙のカケラとしての人間の認知機能にも、宇宙の根源的性質としての“ゆらぎ”が投影されているからであり、その事実こそが、宇宙と音楽が人間にとっての究極の癒しになりうることを物語っているのでしょう。
平均律クラヴィーアを提案した理由
バッハは、平均律クラヴィア第1巻、第2巻の中で、音階として可能な全部で24の調性をもつ楽曲からなる作品を残しています。そのなかの第1巻、1番は、ハ長調の5声部からなる作品ですが、全体が宇宙の根源的性質としての“ゆらぎ”構造(フラクタル)をしており、しかもバスの音の進行が、自然風にあおられながら重力によって落下する落ち葉の“ゆらぎ”そのものであることから、地球の自然を語る絶好例であると考え、ゴールデンレコードへの収録を進言、しかし、実際には、第2巻の1番だったことを後で知りました。ともあれ、NASAがバッハの作品に関心を示していたことは、収録された32曲のうち、3曲がバッハであることから窺い知ることができます。
本公演にご来場される皆様へ
古今東西、全世界の人々に、分け隔てなく同じ姿を見せてくれるのは、星空でしょう。その一方で、音楽には、国や言語、時代を超えて人々を結びつける力があります。つまり、全世界の人類に共通する舞台は、星空の下であり、音楽は世界の共通言語です。その意味からすれば、星空の下で音楽を聴くことは、間違いなく世界平和への第一歩になるでしょう。思い返せば、今から82年前、太平洋戦争のさなか、東京初空襲の直後、宮澤賢治に傾倒していた当時のクラス担任の先生に引率されて、はじめてプラネタリウムと出会ったのがここ有楽町にあった東日天文館でした。これからも、プラネタリウムと音楽が、平和へのゲートウェイであり続けてほしいものです。